ベートーヴェンのピアノソナタはそのままピアノの歴史といえます。
L.V.ベートーヴェン(1770-1827)はピアノソナタを32曲以上残していますが、その一つ一つの曲を独自の世界を持つ個性的な作品に仕上げています。
作曲家が求める音楽にピアノ製作者も応えようとし、そして作り出されたピアノにまた作曲家が刺激を受けて音楽の世界を広げる、という
画期的な時代でした。
これらのソナタは、その特徴から3つのグループに分かれます。
各々のグループのソナタ特徴と、そのとき使用されたピアノとの関わりを見てみましょう。
| 時期 | 使用楽器 (音域) |
|
(1780-1790) |
(ウィーン) 61鍵(1F〜f 3) |
|
| 中期 (1795-1805) |
エラール製 (フランス) 68鍵(1F〜c4) |
|
| 後期 (1808-1822) |
ブロードウッド製 (イギリス) 73鍵(1C〜c4) |
![]()
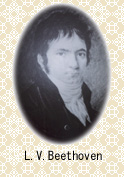 ここでベートーヴェンの作品(特に中期)についてもう少し詳しく見てみましょう。
ここでベートーヴェンの作品(特に中期)についてもう少し詳しく見てみましょう。
ベートーヴェンにとっての音楽とは、まさに人の創るものでした。
それはバロック時代を代表するJ.S.バッハにとって音楽が神聖なものだったのとまったく対照的です。
彼は音楽のスタイルをどうするかという問題についての確実な手腕、磨きぬかれた仕上げと圧倒的な
クライマックスにもっていく展開力、ダイナミックな力強さ、簡潔で要を得た表現力、緻密な論理性を備えていました。
彼の音楽の基本的特徴であるダイナミックな生命力 がどんなところから感じられるのか、具体的に考察してみましょう。
![]() その1.短調の曲が多い
その1.短調の曲が多い
モーツァルトのソナタには長調が多く、透明感のある和音の響きが印象的だが、
それとは対照的にベートーヴェンの意味ある曲はほとんどは短調で作曲されている。
烈しい情緒を主張するヘ短調のソナタが3曲もある。
![]() その2.主題のデザイン
その2.主題のデザイン
ハイドンの主題が大きくて単一的なのに比べ、ベートーヴェンは短いがコントラストの大きい動機をうまく使っている。
中期のソナタではほとんど全ての主題は上昇するデザインを持っている。
例:
| 作品2-1から |
|
| 作品10-3から |
|
| 作品22から |
|
![]() その4.幅広い音域
その4.幅広い音域
ピアノの音域を幅広く活用している。特に豊かに鳴る低音域の和音で力強さを出し、
同時に高音域のパッセージを奏でることなどにより、一層のダイナミックな表現を演出している。
例:
| 作品53「ワルトシュタイン」から冒頭部分 |
|
| 作品57「熱情」から |
|
ベートーヴェンの直接の後継者として知られている作曲家は
F.シューベルト(1797-1828)です。彼はちょうど古典派からロマン派へさしかかる時期に活躍しました。
多くの歌曲を生んだシューベルトのピアノ曲は旋律が美しく息の長い傾向があり、来るロマン派の音楽を予感させるものがあります。

|

|

|